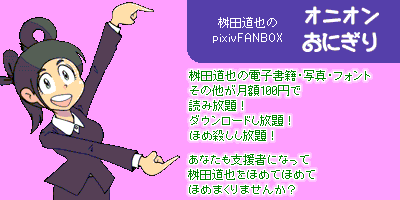ニホンウナギの未来が絶望的と言われた年の土用丑の日に開高 健『フィッシュ・オン』『もっと広く(下)』を読む
今月のはじめにこのようなエントリが話題になった。
ニホンウナギがどれぐらい終わっているのかについての図 – Muchonovski always get it wrong
http://muchonov.hatenablog.com/entry/2013/07/03/210532
これを読んだ数日後、文藝春秋WEBの次の記事にこんなブコメを書いた。
鮨ネタがどんどん消えていく | 特集 – 文藝春秋WEB
http://gekkan.bunshun.jp/articles/-/822
mitimasu その三十年前に開高健が「魚がとれなくなった。こんなことは初めてだ。─と、世界中のいたるところで聞かされた」と書いてるんですけどね。
せっかくなので、今年の土用・丑の日に故・開高 健が魚の減少について30年~40年前に語っていた部分を読み返した。マゾか自分は。
いま、手元にある開高 健の著書は5冊。釣り紀行が4冊、エッセイが1冊だ。あんまり小説家としての開高 健のファンじゃない。小説もどれか一冊は読んだはずなのだけど、感銘を受けなかったようでもはや書名も思い出せない。そんな話はどうでもいいか。
以下、『フィッシュ・オン』から。世界を回っている本なので、当時の各国の水産資源への取り組みが俯瞰でわかる。昭和 49 年(1974)発行だから、2013 年からほぼ 40 年前だ。
 フィッシュ・オン (新潮文庫)
開高 健
フィッシュ・オン (新潮文庫)
開高 健
新潮社
Amazon.co.jpで詳細を見る
アラスカ
私がサケやマスを釣ろうとして道具箱から三本鈎のついたルアーをとりだすと、彼は柔軟だがきびしい口調で、
「一本鈎《シングル・フック》です」
といい、私がそれを持ってないと知ると、自分のをとりだし、ヤスリやペンチを使って、長い時間をかけてとりかえるのだった。自然保護政策のことを見聞した範囲内でのみ書いておこう。これは重要なことだ。 アラスカはおそらく川と湖と海に魚があふれかえっているくらい豊穣《ほうじょう》な土地で、 私たちが回生できる文字通りの〝最後の開拓地〟であるが――そこに住む人は荒廃するかもしれないが――自然は透明な方法で厳しく管理されている。
私が訪れた地区では、たとえば、どんな魚を釣るにも一本鈎でなければならない。 錘は針の直前、直後につけてはならない。鈎軸と鈎先は二分の一インチ以上ひらいてはならない。 生餌を使うとき、それが小魚なら、きっと殺してから使わなければならない。 ひっかけ釣りの鈎はふところが四分の一以上ひらいてはならぬ、とされていた。 そして、バグ・リミット(一日にとってよい魚の数)は、魚によって異なるが、たとえばキング・サーモンについてこれを見ると、一日に六十六センチ以上のは二匹、それ以下のは十匹とされていた。
まるで障害物競走である。<中略>
たいていのルアーについてるのは三本鈎である。これを一本にとりかえる。三本の指がサケの口にかかるのと、たった一本がかかるのとでは、力の効果にひどい相違がでてくる。魚の受ける傷がちがってくる。弱り方がちがってくる。しかし、同時に三本鈎なら死んでしまう魚も一本鈎なら逃がしてやったときに生きのこれる確率は増すのである。
40 年後の日本で、自然を守るためにここまで厳しいルールを課している自治体があるのだろうか。私はもう長いこと釣りをしてないのでよく知らないけれども。
もっともアラスカだって守ってるのは自然だけじゃなくて、ガイドを始めとした釣り産業を守るためなんだろうが。それにしたって、”その川のサケがいなくなったらお終いだ”ってことは理解してやっている。 捕り尽くしたあげく、いなくなったから他所のサケを代用に……なんて考え方はしていない。
アイスランド
「サケはたくましいけどデリケートな魚です。原因不明の病気で死ぬことがよくあるのです。 竿を消毒《ステリライズ》したからといってその病気が防げるとはわかっていませんけど、アイルランドとイングランドで釣りをした人の竿は消毒することになっているのです。ほんの五分ですむことですけどね」
「釣竿を消毒する?!」
「そうです」
「釣竿を消毒?!……」
「わが国の規則なんです。でもあなたはアラスカとスウェーデンで釣りをしたのですから、それならかまわないと、いまサケ釣り協会の人が言ってくれました。消毒の必要はありません」
ややもすれば、アングロサクソンの完全主義的な行き過ぎた例か。開高 健も自然保護の狂熱にも似た情熱のきびしさ
と評している。
……たんなる、ブリテン嫌いから生じた差別だったりして。
ギリシャ
今回の旅で私は木のない国を二つ、あらためて知らされた。アイスランドとギリシャである。 アイスランドは北極圏に近く、かつ、無数の火山弾の襲撃でツンドラの苔以外の植物が根をおろせなかったらしい兆候がいたるところに読みとれるが、 ギリシャが古代からこうだったとすると、あの大建築、大航海、大戦争、大海戦を遂行するのに必要な木材をどこから入手したのだろうか。 もし古代は鬱蒼《うっそう》と巨木に蔽《おお》われていたのだとすると、全土にわたってこうも剃刀《かみそり》で剃《そ》ったようにきれいさっぱり乱伐して省みなかった事情とは何であったのだろうか。
小アジア・ギリシャ・イタリア・スペイン・イギリスと、石炭コークス発明以前に大量の鉄を必要とした国はことごとく森が消滅してますね。これらの国は気候的にも巨大な針葉樹が育ちにくい国でもあるんですが。
西洋の自然保護意識が高いのも、単純に、”まっ先に産業革命による自然破壊を経験したから”に他ならない。
それを見て、反面教師にできるか、できないかがその国民の民度ってやつじゃないかと思うのだけど。
タイ
「あなたはバカではないか」
といった。
「どうしてです?」
「私の部下がそういうのです。あなたはバカではないかというのです。竿なんかなくても釣れるのに竿を使うし、釣った魚を逃がしてやっている。ボートを高い金で借りながら釣った魚を逃がしてやっている。いったい何のために魚釣りにきたのです?」
「魚を逃がしてやったら、ふえますよ。そうすれば漁師もよろこぶし、つぎにくる釣師もよろこぶし、私もつぎにきたとき、また釣れるじゃありませんか。それに私は遊びで釣りをしているので、漁師じゃありませんよ。釣ることには夢中ですけど、殺すことには興味がないのです」
「タイにはいっぱい魚がおります。タイ人は河の魚は食べるけれど、海の魚は匂いがするといってあまり食べません。値段もぐっと安いのです。魚を逃がしてやる必要はありません。漁師にやりなさい。よろこびますよ。どうせ彼らは魚をとらねばならないのです」
このタイ人の感覚が、一般的な”まだ自然破壊が深刻でない国”の感覚だろう。
40 年たった今でも、ニッポンの釣り好きのオトーサンはたまに入れ食いに当たると嬉しくなっちゃってクーラーの限界まで釣っては、もちろん食べきれないので近所におすそわけする。 それが美風とされている。
日本
イワナが条件次第ではサケのように大きくなれるというこの実例にはホッとする。 このあたりには田も山畑もないから湖には農薬が流れ込まないはずである。魚を減らすのは釣師だけである。 釣師がめちゃをやりさえしなければ深くて広くて純粋な水の中では自然が回転するだけである。<中略> 同じような条件にある山上湖は日本に多いので、いまからでも遅くはない、ちょっと大事にしてやればいたるところで抹消、絶滅して、もう魚類図鑑にさえのらなくなっている日本産淡水魚がよみがえってこれるはずである。
開高 健が釣師であるためか、こうした兵器好きの反戦論者みたいな矛盾をはらんだ問題提起になると、筆が鈍っている…正直、平凡な意見に終始してしまっている。
湖の遊覧船に乗りにくる客や、駒ヶ岳、荒沢岳などにのぼる登山客や、キャンパーたちも来るけれど、ここでいちばん多いのは釣師である。その釣師がじつはやらずぶったくり方式で湖をからっぽにしていくのだから宿の主人としては歓迎したらいいのか拒んだらいいのかがわからない。
佐藤進は何度となく不定愁訴した。
「お客さんがこげな小っこいのを釣ってきて魚拓をとれの、どうしろのといいだすと、おらは痛いぜや。手足の指のどれかを切られたみたいな気持だ。太《でこ》いのを釣られてもそうだ。何年か昔にくらべると太《でこ》いのも小っこいのも釣れなくなってきたんだ。銀山湖じゃねえ。貧山湖だ。からっぽの金魚蜂ってとこだな」
さて、いまとなーんも変わらない 39 年前の日本を読んで鬱になったところで、9 年後の 1983 の本を読んでみよう。
 もっと広く!―南北両アメリカ大陸縦断記・南米篇 (下) (文春文庫 (127‐10))
開高 健 水村 孝
もっと広く!―南北両アメリカ大陸縦断記・南米篇 (下) (文春文庫 (127‐10))
開高 健 水村 孝
文藝春秋
Amazon.co.jpで詳細を見る
ペルー
ここへ来た初日の朝に私は磯岩によじのぼって釣りをするうちにその長上から沖をなにげなく望見して驚愕にうたれた。その後、毎日、朝と夕方に、正確におなじ時刻にその驚愕は出現しくりかえされるのだが、私はいつも目を洗われて、恍惚となる。何千羽、何万羽、数知れぬウ(鵜)の大群が二列か三列の乱れた縦列となってゆっくり羽ばたきつつ南へおりていく光景である。 その羽ばたきぶりがゆっくりしていること、 十分、二十分、凝視していても、つぎからつぎへとめどなく平然として行列が続くこと、 この二つのために私はいつも今度こそ最後尾を見届けてやろうと、 釣り竿を岩にたてかけ、新しいタバコに火をつけて、眼をこらすのだが、 いつも根負けしてしまう。それで、ついつい釣竿に手をのばして魚を釣りにかかるのだが、 これまた根負けして、ふと眼をあげると、沖ではまだ鵜の行列が続いているのだ<中略>
「すごい。ドン・ルーチョ。すごいよ。私はこれまでにいくらか世界のあちらこちら歩いてきましたが、 こんな鳥の大群を見るのははじめてですね。ペルーのフィッシュ・ミール(魚粉)は世界のニワトリを養っていると、かねがね聞いていますが、これほどだとは知らなかった。すばらしい光景です。これを見れただけで満足ですよ、私は」
テント村に戻って感動をおろおろ語ると、ドン・ルーチョは慎重に耳を傾けて聞き、聞き終わるとそのフットボールくらいもある丸い大頭をもたげて、半ば誇らしげに半ばいまいましげに、冷静な口調で、二十年前、または十五年前にくらべると、このあたりの鳥だけでも目算したところ、八〇パーセント減っちゃったですと、いった。<中略>
開高さんに鵜の群れをほめて頂くのはうれしいですけど、あなた、これは昔の二〇パーセントにすぎないですよ」
「どうしてそんなに減ったの?」
「とりすぎですよ。どいつもこいつもイワシをとりはじめた。海のゴールド・ラッシュですな。人間の欲です。いつも人間です。人間ですな」
「政府はコントロールしないの?」
「政府は底のないバケツですな」
強調部は引用者(つまり私)によります。
この本が出た 1983 年を冒頭に紹介したサイトで見ると、シラスウナギの漁獲高がだいたい 20 年で 80% くらい減っているので、国も魚の種類もちがうけど、全世界的に多くの魚でソレが起きてたのではないかと思える。
ドン・ルーチョふかしこいてない。
これが、2013 年のいまから 30 年前だ。30 年でニホンウナギは絶滅ほぼ確定にまで至ったが、ペルー沖の鵜の大群は今でも存在しているのだろうか。
アルゼンチン
季節はずれでダメだ、ダメだとブエノスアイレスで聞かされたにもかかわらず、ふたたびのりだしてきたのである。
なぜダメかというと。
- ドラドの季節は七月、八月、九月である。今は二月である。もう半年待ちなさい。
- 最近はダム工事や工業開発がさかんでパラナ河もパラグァイ河も上流のジャングルが乱伐されて、ちょっと雨が降るとドロドロになる。
- 釣師の数がめったら増えたうえ、政府が肉より魚を食えの宣伝をすることもあって、河の沿岸の漁師たちが産卵期も何もおかまいなしに日本製のナイロン網で乱獲する。トラック一杯に山盛りの親魚をはこんでいる日系釣師がいる。思わず声をあげて抗議したけれど、セセラ笑われただけである。
①についてはどうしようもないが、②と③については耳にタコができるほど聞かされて、それが世界中のあちこちでだから、いまやピクリともしなくなった主題である。〝工業化〟と〝人口爆発〟である。 魚が住みにくいところはまわりまわって結局のところ人間にも住みにくいところなのであるという原理は、 考えられ、説かれ、書かれつくしているけれど、現実においてはバラのトゲに刺されたほどにも感じられていないのである。先進国が自然をめちゃくちゃにして、そのあげく、その結果として、電化生活や、洗剤や、何や、かやを入手したのに、開発途上国がおなじ物をおなじ手段で入手しようとしたらにわかに反対しだすとは何事だと、途上国の指導者たちは叫ぶのである。その主張はまことに理の当然であるから、 誰もがモグモグとだまってしまうよりほかない。だからこそオレたちの真似をしちゃいけないんだと、エアコンのきいた部屋でコカコーラをうんざりした手つきでつまんで誰かが叫んでも、 途上国の留学生や指導者たちはいよいよ反感を燃やして激昂するだけのことであろう<中略>
つまり、これを要するに、地球は北半球も南半球もおかまいなしに、よってたかって穴ボコ、剥げちょろけ、枯渇、洪水、日照りという具合なのであって、そんなことはとっくに五十年も百年も前に書かれつくしてしまったことである。われらは既知の道をたどって未知の国に向かいつつあるの一言あるのみ。 私個人についてこれを見ると、八ヵ月かかってアラスカから南下してきて、大汗かいて、ダニやブヨでぶくぶくになって地球の裏側までやってきて、とっくに湘南海岸の書斎でおそらくはこうであるだろうと予測をたてた、まさにその通りの声を聞かされるだけの、巡礼であった。
強調部は原著では傍点。
十年前には、まだなんとかしたいという気持ちが見られたが、このころにはもうすっかりあきらめの境地にいたっている。
そして、7年後の『オーパ、オーパ!!』になると、もはやこの問題にはほとんど触れなくなってしまっている。
以上の文章を読んでわかることは、シラスウナギの件も、30 年前にそうなることがわかっていて、でも止められず、なるべくしてそうなったということだ。
われらは既知の道をたどって未知の国に向かいつつあるの一言あるのみ
さらに 20 年後か 30 年後、サンマが食卓から消えたとき、私はまたこの本を引用するのだろうか。
……と、上で結んだのち、6年後の 2019 の状況を以下に記す。
追記 2019 年 12 月
>サンマすっかり「高級魚」 県内、記録的不漁 | 岩手日報 IWATE NIPPO
https://www.iwate-np.co.jp/article/2019/12/7/69322
>今季の本県サンマ水揚げ量(11月末現在)は前年同期の31・9%にとどまり、平成以降で最低水準に終わる見通しだ。
漁獲高が少なかったのは海水温が下がらず、来遊量が減ったためであり、必ずしも乱獲のせいとは言えない。
しかしながら、1958 年を最高に減少傾向にあるのはあきらかで、手遅れになるまで資源回復を目的とした積極策を打たない政府の先見性の無さは責められるべきであろう。
2019 年のサンマ漁獲高は記録の残る過去最低であった 1969 年を下回る見込みだ。では、その 1969 年の不漁はなぜ起きたのか。
記録を見ると、1964 年から 1972 年が不漁期だ。最低年であった 1969 に向けて急降下し、その後、V字回復している。
当時も原因について、様々に議論があったようである。気候変動は数十年スパンで減ったり増えたりするものであり、水産資源も気候変動の影響を受けるものである、とか、運悪く捕食性の大型魚に食べつくされたのであろう、など。
「食」と「漁」を考える地域シンポ 第19回 太平洋サンマの資源動向と来遊予測
~サンマ水揚でめざそう!三陸のさらなる復興~
https://www.suisan-shinkou.or.jp/promotion/pdf/shokutoryou19.pdf
気候が長いスパンで変動することや、水産資源は周期性があるものだ(だから驚くにはあたらない、いずれ回復する…という含みがある意見と思われる)という論調は、1969 の当時もあったようだ。2019 において、海水温の上昇で来遊しなくなっただけである、水産資源は周期性があるので驚くには当たらない、という主張があるのとよく似ている。
しかしながら、1964~1972にかけて、漁獲高は五年で急降下し五年で急回復している。これほどの影響を与える異常な気候変動は、当時、観測されていない。
これを説明できるもっとも有力な原因は、やはり乱獲でしかなかった。1950~1951 年頃に漁法が流し網漁法から棒受網漁法へと変化し、漁獲できる量が10倍にも増えたのである。それから漁獲高は年々倍増し 1958 年の最高漁獲高につながった。
獲りすぎれば資源が失われるのは当たり前の話で、我が国はニシンでそれを経験していながら、またもそれをやらかしたのだ。
ではなぜ、1970~1972 にV字回復したのか。簡単な話だ。1968~1969の不漁で漁師たちがサンマ漁を廃業してしまったのである。
誰も獲らなければ(回復可能な個体数が残っていれば)回復する。当たり前の話だ。そしてこのときは、日本以外の外国船はサンマに見向きもしていなかったので、日本人がサンマを獲らなければ、資源はみるみる回復したのである。
さて、2019 年。いまや、サンマは諸外国も獲るようになった。台湾の水揚げ量は日本を抜いたという。もはや、日本だけ我慢すれば回復するわけではなくなってしまった。
どうする?



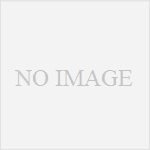
![[鉄旅] 2012夏 訪城の旅 後編 備中高梁ほか](http://blog.masuseki.com/wp-content/uploads/2012/10/07e519430eb2658deb02f6a6f4e3f52b-100x100.jpg)